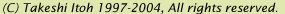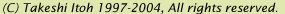TYLER, ANNE /アン・タイラー
| 夢見た旅 | フォード | EARTHLY POSSESSIONS, (c)1977 | 早川,1987 |
|---|
- 『いいか、そんな事を言われてもまだ我慢したぞ。じっと穏やかに、フォードへ戻っていった。爆発しそうな気持ちだったが、じっと黙っていた。車に乗り込んで、エンジンをかけ、バックするためにミラーをちゃんとなおした。でも、おれはバックしないで、前へいった。どうして、そんなことになったのか、見当もつかないんだ。やるつもりではあったが、実際にやってしまうとは思わなかったからな。
おれがまっしぐらに車の陳列場へつっこんだんで、マーヴェルは左へ跳びのき、客どもは右へ跳びのいた。新車のベルエアにぶつけて、右側全体がへこんだ。
バックしてこんどはヴェガにぶつけた。一列全部、がつんがつんぶつけてやった。フェンダーは紙みたいにくしゃくしゃになるし、バンパーも曲がり、ドアがとれた。ぶつける度に、こうバリバリ、バリバリって音がしてさ誰も彼も悲鳴を上げて跳ね回っていたな。もちろん、おれの車もすこしへこんだが、たいしたことはなかったんだ。実際、そのまま運転して帰ることもできただろうね。だが、おれはモンツァに正面衝突してやりたくなっちまってさ。あのな、ダービーでは正面衝突はやらないんだ。反則になるんだ。だから、やりたい衝動にかられた。正面からぶつかっていったら、車二台、独立記念日の花火みたいに爆発したぜ。おれは大急ぎで走り去ったが外で三人のおまわりにつかまった』
--COMMENT--
少し前にタイラーの「アクシデンタル・ツーリスト」を読んで気に入ったので、再び手にしたが、そこはかとないユーモアとごく普通の人を題材とした登場人物へのあたたかい眼差しがやはりよい。アメリカのいなかの生活から脱出しようとした主婦が、ふとしたはずみで銀行強盗の人質にとられ、思いもしなかった旅に付き合わされる事になる。
上の引用は、この若い無鉄砲だが根はにくめない銀行強盗の告白の部分。ダービーとは、ディモリッション・ダービーのことで、スタジアムでの車のぶっつけあいのことらしい。逃走に使う車は、車名はでてこないが、クラシック調に改造したおかしなモデルであり、ストーリーの大半がその車でのシーンである。(93/10)
| アクシデンタル・ツーリスト | トヨタ、ビィック、ワーゲン | THE ACCIDENTARL TOURIST, (c)1985 | 早川, 1989 |
|---|
-
『「おたくは今は何に乗っているんだね、メイコン?」
「乗ってる? ああ、トヨタです」
デュガン氏は顔をしかめた.クレアがくすくす笑いながらメイコンに言った。「パパは外国車が嫌いなの。毛嫌いしているのよ」
「それはどういうことなのかな、おたくは国産品を信用していないのかね?」
「シボレーを試してみて下さいよ、メイコン。いつかショウルームにおいでなさい。私が案内するから。おたくの好みは? ファミリー・サイズ? それともコンパクト・サイズ?」
「まあ、コンパクト・サイズですけど、でも」
「じゃひとつだけ言わせて下さい。私はね金輪際どんな事があってもサブコンパクト・カーは売らないんです。それだけはダメだね、頼まれても、泣かれても、ひざまずかれても、あんな死の落とし穴みたいな代物は絶対に売らないんです。騙されてあれを買っている人が最近多いようだけど。私はお客に言うんですよ、“あなたは私に信念がないとでもお思いですか?”ってね。
“あなたの目の前にいるのは信念を絵に描いたような男なんですよ”ってね。
“それでもサブコンパクト・カーがほしかったら、エド・マッケンジーの所へ行きなさい。彼なら何も考えずに売ってくれますから。このミュリエルも、サブコンパクト・カーで危うく命を落としそうになったんですよ」』
--COMMENT--
珍しく女性作家の恋愛ものを手に取りましたが、迷いの多いごく普通の旅行作家メイコンを中心として、生き生きとしたペーソスと笑いが新鮮でけっこうまっとうな小説らしい小説でした。
私の好きなR.B.パーカーのタッチと似ているようです。上のシーンは、メイコンがなんとなく好きになった彼女、ミュリエルの両親の家へ始めて招かれ、車のセールスの父親からひとくさりやられるところ。ほかにも楽しい車のシーンがたくさんある。(93/09)
| パッチワーク・プラネット | ボルボのステーションワゴン | A Patchwork Planet (c)1998 | 中野恵津子訳 文春, 1999 |
|---|
-
『「気がつくと、ある日突然、僕は窓のそばに立ってドライブウェイを見おろしていて、ナタリーは赤ん坊のオーバルを車に押し込んでいた。あの車は、オーバルが生まれたときに彼女の親がくれたボルボのステーションワゴンでね、僕はナタリーが助手席のドアを閉めて、運転席にまわるのを見ながら、思わず口走っていた、『ひぇー!俺って、いわゆるステーション・ワゴン・ママと結婚してたんだ!』なんてね。そして、二人は離婚した、というわけ」
ソフィアは自分の指をなめるのを中断した。「すぐに?」
「いや。すぐにじゃない。はじめはいろいろゴタついたけどね。確かに、僕が模範的な亭主じゃなかったことは認めるよ。結局、彼女はオーバルを連れて出ていった。僕にひとこともなく。出直しのチャンスもくれずに。」』
--COMMENT--
待ちに待ったタイラーの最新作。ボルチモアに住むお年寄り向けのお手伝いサービスをやっているバーナビーが(男性が主人公になるのは珍しい)フィラデルフィアにいく列車でソフィアと出会い、人生が変わり始めたと思ったが・・ いつものタイラー節とも言える、人々をみる細やかで暖かい語り口と、ユーモア、そしてほろ苦い顛末が魅力だ。
上記は、バーナビーとソフィアの会話だが、"ステーション・ワゴン・ママ"なんていう言葉は知らなかったが、なんとなくニュアンスが伝わってくる。当人が叔父さんからもらった63年型コーヴェット・スティング・レイのクーペ、仕事仲間の"でこぼこの赤いピアップ・トラック"、銀行員ソフィアのサーブ、兄貴の"よくあるマッチョ・タイプの四輪駆動車"、子供の頃からの悪友達の黒いレクサス、母親の"豪華でメチャ高いビュイック"など多彩なクルマが登場してくる。(1999/09/23)
| あのころ、私たちはおとなだった | シヴォレー | Back When We Were Grownups (c)2001 | 中野恵津子訳 文春, 2003 |
|---|
-
『レベッカの車は84年型のシヴォレーで、点々とさびが浮き、音がうるさく、急なカーブに差し掛かるとめまいがするほどふらついた。(レベッカはいつも、プランターにしてしまうわよ、とシヴォレーを脅していた。)前にも後ろにも、孫達の残していったファーストフードの空き袋や、ソフトドリンクの缶、古い漫画本、くしゃくしゃになった汚い運動用ソックスなどが散らかっていた。どうしてきれいにしようと思いつかなかったのか、一瞬、怒りが込みあげてきた。昔のレベッカは、いつも物をきちんと片付けておくタイプだったのに、ダヴィッチ家の人々と出会う前は。
最初のうちはふだんと変わらないドライブだった。いつもと同じ、いかめしい感じの古い建物を通り過ぎた。住宅用に建てられた背の高いその建物群は、今ではほとんどがオフィスや店舗や安アパートに改造されている。レベッカは南へ進路をとり、コインランドリーや中華料理店、酒屋、閉店した食料品店などが並ぶ通りへ入っていった。
ラッシュアワーはほぼ終わり、一連の交差点もスムーズに通り抜けた。赤信号で停まったとき、一人の少年が、セロファンの筒に窮屈そうに閉じ込められたバラを売りにきた。次の信号では、冬のジャケットを着た青白い男が、<私は空腹で、病気で、疲れていて、惨めな思いをしています>と書かれたプラカードを掲げていた。汚れた雑巾とガラス洗浄液のビンを持った子どもが近寄ってきたが、レベッカは頭を横に振った。』
--COMMENT--
<むかし、あるところに、自分の思っていたのとはぜんぜん違う人間になってしまったと気づいた女がいました。そのとき彼女は53歳、すでに孫までいました:書き出し部分>・・4年ぶりの新刊で、うーむ、タイラー節、そのままだし、主人公レベッカの包容力あふれるキャラクターはとても魅力的だった。
引用したシーンは、学生時代の元恋人に三十年ぶりに会いに行く場面。('03.8.2)
| 結婚のアマチュア | ダッジ・スペシャル | The Amateur Marriage (C)2004 | 中野恵津子訳 文春 2005 |
|---|
-
『車は1940年型のダッジ・スペシャルだった。色はつや消しの黒。亀の形をしたこの車は、父が薄いピンクのデラックスに乗り換えたときにもらったものだ。マイケルはまだ運転の仕方も知らなかったので、ポーリーンが教えてやらなければならなかった。
彼は出来すぎの生徒だった。今では、店へ送っていく彼女の運転に、ギア・チェンジがおかしい、なんでそんなにエンジンをふかすんだ、と口をはさんだ。ポーリーンは車をバックさせて道路へ出て行ったが、ステーション・ワゴンが近づいてくるのに気がつかず、クラクションを鳴らされてブレーキを踏みこみ、ひやっとしながら家のほうを見た。マイケルには聞こえなかったらしい。窓辺にでてこなかったから。』
--COMMENT--
5月に発行され、即日入手していたけど、アン・タイラー本は特別の愛着 ― 何故だがよく説明できないのだが ― があってじっくり読んだ。
パールハーバーの日にお互いに一目ぼれして結ばれたマイケルとポーリーンが、なに不足ない結婚30周年をむかえたものの結局のところ、性格の不一致から別居・離婚。ごく普通の夫婦のしみじみとして、ほろ苦いやりとりを暖かく見つめる絶妙なタッチは心に染み入るようだし、身につまされる。
読み取り方はいろいろあろうが、ほとんどの結婚は“アマチュア同士”であって、乖離が表面化するかどうかはほんの僅かなバリエーションだよ…と言っているような気がする。
なんせ60年もの間の物語なので車もいろいろでてくる。ポーリーンの80歳を過ぎた父親が娘を心配して訪ねてくる時にドライブしてくるのが"つやのある黒のビュイック"、離婚してからも、一人で住むポーリーンの家のドライブウェイを除雪にきたり、彼女のシヴォレーのオイル交換をしにきたりするマイケル…なども描かれている。(2005.8.28 #368)
| ノアの羅針盤 | カローラ | NOAH'S COMPASS (C)2009 | 中野恵津子訳 文春 2011 |
|---|
-
『そして9時近く、人が到着し始めた。スーツ姿の若い男たち、あらゆる年齢層の女たちが、二人三人とかたまって歩き、しゃべったり、笑ったり、肘をつつきあったりしながら建物のなかへ入っていった。リーアムは、いっしょに働く者同士の仲間意識が懐かしくて、少し胸がうずいた。
つなぎの作業服を着た男がリーアムのそばを通り過ぎ、停めてあったパネルトラックに乗って走り去った。その直後、まるで示し合わせていたように空いたスペースに薄汚れた緑色のカローラが滑り込んできた。運転席から女がおりてきた。記憶係だ。今日もエスニック風の大きなスカートをはいているが、ひょっとしたら先日と同じスカートかもしれない。厚さのせいでカーリーヘアの巻き毛が濡れているように見える。彼女はカローラの後ろを通って助手席へと回った。
リーアムの目の前を通ったので、道路を引きずるサンダルの音まで聞こえた。彼女が助手席のドアを開けると、コープ氏が座席からゆっくり降りてきて、腰を伸ばしてまっすぐに立った。』
--COMMENT--
『結婚のアマチュア』以来、6年ぶり邦訳13作目の本書は、60歳になって学校からリストラされた教師が、偶然出会った記憶係のユーニス(物忘れのひどくなった経営者の秘書役)と、教師の別れた妻と娘たちとのふれあいを通じ老境を考える。どこにもいそうなごく普通の人たちの心の機微が、ユーモアと情感をこめて語られる…タイラーはやはり随一ですね。
引用は主人公のリーアムがユーニスの出回り先に出かけるシーン。カローラが登場するのは近年のノヴェルではかなり珍しい。もっとも、リーアムの車もジオ・プリズムで、娘たちからいい年の男が乗る車じゃないとくさされる。他に、リーアムの父親の"はしけのように大きなシボレー"、娘の"赤いジェッタ"など。ユーニスの夫の"売りに出された最初の年から乗ったプリウス"…ついにノヴェルにもハイブリッドが登場するようになったなぁ。(2011.10.26 #714)
作家著作リストT Lagoon top